原 題 「COVER HER FACE」1962年
著 者 P.D.ジェイムズ
翻訳者 山室 まりや
出 版 早川書房 1977年5月
単行本 253ページ
初 読 2022年3月17日
ISBN-10 4150012814
ISBN-13 978-4150012816
翻訳が今の感覚からすると古臭いのはいたしかたないとして、訳が直訳調で、高校生の長文和訳の宿題ノートみたい。ところどころ文脈がよくわからないし、訳語の選び方もちょっと。内心思っていることをいちいち“ ”で括って
・・・”と◯◯は思った。
ってやるのも、煩わしいよな。「害者」(ガイシャ)「ほし」(ホシ)「やる」(殺る?)って、時代的になんとなく「太陽にほえろ」や、毎週テレビでやっていた「なんとかサスペンス」とか「◯曜ワイドショー」みたいな2時間枠のドラマを思い出すなあ。でも、上流の家庭に捜査に入った品のよい刑事ダルグリッシュが使うにはなんともガサツ。
ジェイムズの作品は、早川が新版発行に取り掛かっているようなので、ぜひ新訳での刊行を望みたい。個人的な事情ながら、今、ちょうど年度末で死ぬほど忙しく、睡眠不足を押して本を読んでいるので、1行読むごとに眠くなる翻訳は困る。
それでも、他ならぬダルグリッシュのシリーズ一冊目なので頑張って読む。田舎の旧家の人間関係のあれこれ、登場人物の誰一人として好きになれず、感情移入できないまま、とにかく事件が起こるまで忍の一字で読む。とにかく人物造形を書き込んで、やっと殺人が起こったのは全体の1/4くらいのところ。
そこからは事件の捜査のために、地方警察を支援するかたちでヤードからダルグリッシュが派遣されてくるので、比較的サクサクとすすむのだが。
意外だったのが、ダルグリッシュが妻と一人息子を出産で失った、というのが初期設定だったことかな。先によんだ『死の味』はシリーズ中盤の作品なので、ダルグリッシュの結婚やら、妻と子の死のエピソードはシリーズ中で起こるのかと思っていた。
こうしてみると、1962年(作中でも、まだ戦争の記憶が生々しい。)から、2000年頃まで、警部→警視→警視長と出世こそすれ、あまり歳も取らずに作品世界だけが時代を経過している、というのも、(キンケイド警視シリーズなども同様だが)長寿ミステリー小説のミステリーだ。
ところで、「オーヴァルティン」という寝しなの飲み物がでてくるが、これは英国で昔から飲まれているチョコレート味の麦芽飲料だそう。ミロみたいなものかな?イギリス人のチョコレート好きは相当なもので、鉄道の駅にチョコレートの自動販売機が設置されている、と教えられたのはかれこれ・・・・大昔の学生時代だが、この田舎の名家の家族は一家揃ってチョコレードが嫌いだが、台所には、それでも来客や召使のためにココアやオーヴァルディンが用意してあるようだ。
さて、ストーリーは、ロンドン郊外の村で起きた、殺人事件。
殺された女性は、裏が、というかいろいろと事情のありそうな未婚の母。この、「未婚の母」に対する風潮も、いかにも60年代、女性に求める貞操観念もいまとなっては時代がかっているし、未婚の母を収容する「女性保護施設」があるのも時代だな。(むろん、未婚の若い母子を支援する施設は今だってあるけど、ちょっと意味合いが違うような気もする。)
登場人物も戦争の記憶を生々しく背負っている。元レジスタンス、傷痍軍人、元は軍人あがりの使用人、戦争孤児。登場人物はみな、戦前/戦中生まれだ。60年代というのはそういう時代だったのだな、と改めて思う。
ダルグリッシュが、周辺の関係者から証言を集めて犯人を推察していくのは、先によんだ『死の味』と同じ。このスタイルは最初から確立されていたようだ。
ただ、まだダルグリッシュの持ち味はさほど出ていない。むしろ、狂言回し役。あくまでもシリーズ一作目。作詩のエピソードも自作から。次作で、彼はもうすこし光ってくるかな。
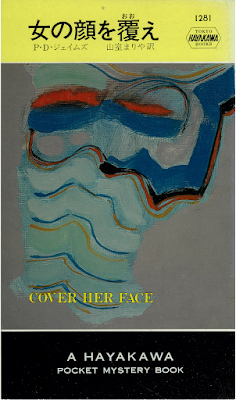
0 件のコメント:
コメントを投稿